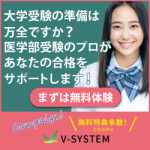大学入学共通テストも新課程となり、その一年目。
国語の大問追加、数学ⅡBCの選択問題追加、歴史総合、地理総合、公共の追加・・・
そして、極めつけは 情報Ⅰ という新しい科目の追加と膨大な負担増を強いた入試でした。
が、内容は国語・数学の易化、情報Ⅰの取り組み易さと、文系・理系ともに平均点は昨年よりも
プラスとなり難関大志向の強い国公立大学の出願先相談が多い印象です。とはいえ・・・
一番多いのは『C判定』で出願するべきですか?という質問です。
最後は親でも、学校の先生でも、塾・予備校の先生でもなく自分で決める必要があります。
が、ひとつの考え方を示しますので参考になれば幸いです。
※蛍雪時代 1月号には【共通テスト 自己採点結果別 第1志望? 第2志望? の判断】という
特集が組まれています
共通テストの難易度はどうだったのか?
『課程変更の初年度は易化する』の流れ通り、全体的に取り組みやすい出題でした。
特に平均点に大きな影響を与える “国語” と “数学ⅡBC” が思ったよりも取り組み易かったことが一番の要因かと思います。
まだ平均点は各予備校の中間集計しか出ていないので明言はできませんが、、、
■東進(文系) 621点(62.1%) ※昨年 539点(59.9%)
■東進(理系) 636点(63.6%) ※昨年 564点(62.7%)
■河合塾(文系) 620点 ※昨年記載なし
■河合塾(理系) 633点 ※昨年記載なし
文系で2%強、理系でほぼ1% 昨年よりも平均がプラスになっています。
※国語がそこまで荒れなかったのも受験生にはプラスでした。地理が思考問題中心で解きにくい
出題であったことぐらいが特徴といえます※
そして、2日目の数学(特に数学ⅡBC)が予想に反して、易しい出題でした。
大問1・2は定期テストの問題かと感じた受験生も多かったと思います(時間が足りて良かったね♪)
理科は化学の計算が重く、時間が厳しかったと思います。
※第5問の原油の分留とバナジウムに関する問題はかなりの難問だったと思います。
化学の最後の大問が高難度の思考問題であるのは定着したといえますね・・・※
ただ、不思議なこともあります。
それは、問題の難易度から想定されるほど平均点が昨対で高くないってことです。
その要因として『上位勢が異様なほど高得点帯に集まっている』事実の裏で、中間層以下の
ボリュームゾーンの受験生は『そこまで高得点を取り切れていない』という事実があります。
※故に易化と大盛り上がりの一方で、平均点が大きく伸びていないってことです※
東進の合否判定システム や 河合塾のバンザイシステム などを見ていますと、東京大学、
京都大学、東京科学大学、旧帝大医学部などのAラインもさることながら上位ゾーンに膨大な人数が集まっているのは明白です(文系の都市圏国公立大学も顕著です)
一方で、地方国立大学の人数分布をみると例年通り・・・といった様相です。
このことから予想されることは・・・
①難関大学(旧帝大、都市圏大学)は5%程度は昨年のボーダーよりも上がるのではないかということ
理由は、ここまで述べてきたとおりです。
とくに文系の上がり幅が大きく出願は注意が必要です。
理系は最上位大学と医学部で注意が必要です。
②全体的に『イケイケ』の出願になるのではないかということ
理由は、全体的に直前の模試や過去問よりも手ごたえがあり、『上手くいった』と感じているはず。
難関大学への出願を考えている人は、上手くいったのは自分だけではないという事実を冷静に
受け止めてください。
その上で、大学別模試(本番レベル模試やオープン、実戦)の出来具合から自信の二次力が
志望大学のレベルに足るのかを判断しましょう。
浮足立たず、出願大学を調整する勇気が必要な局面と予想します。
③国公立大学の医学部志望者は、全国津々浦々まで検討しましょう
医学部志望者に取って共通テストは最初にして最大の関門ですが、国語も英語も大幅に難化しなかったこともあり差が付いていない状況だと予想されます。
今回の共通テストで88%を超えていない場合は旧帝大、都市圏大学の医学部は厳しいです。
85%付近なら大人しく地方大学 医学部 を検討しましょう(80%なくて医学科は厳しい)

バンザイシステムの判定を1年前だけでなく2年前とも比較する
【国立大学 文系】
大阪大学 経済学部 経済・経営
2025年度共通テストリサーチ(300点満点)
A判定 270 B判定 258 C判定 247 D判定 237
※ボーダー得点 252
1年前 A判定 249 B判定 243 C判定 237 D判定 231
※ボーダー得点 240
2年前 A判定 252 B判定 242 C判定 232 D判定 222
※ボーダー得点 237
神戸大学 経済学部 経済(総合)
2025年度共通テストリサーチ(450点満点)
A判定 378(84%) B判定 366(81.3%) C判定 354(78.7%)
D判定 342(76%) ※ボーダー得点 360(80%)
昨年度まで400点満点だったので得点率も記載します
1年前 A判定 320(80%) B判定 309(77.3%)
C判定 299(74.8%) D判定 288(72%) ※ボーダー得点 304(76%)
2年前 A判定 320(80%) B判定 309(77.3%)
C判定 297(74.3%) D判定 284(71%) ※ボーダー得点 304(76%)
文系は昨年から判定基準とボーダーは『4%程度のアップ』
昨年と比較して、国語・リーディング・数学が易化した影響で文系は大きな事故を起こさなかった
受験生が多かったものと想定されます。
つまり、今年度の共通テストでC判定もしくはそれ以下の判定であれば、二次力に疑問が生じるということですから、『C判定ならワンランク下げる』ことの検討が必要になります。
合わせて文系は共通テストと二次試験の比率が均等の大学が多く、二次逆転が難しいことも念頭に置いておきましょう。
【国立大学 理系(医学部)】
京都大学 医学部 医学科
2025年度共通テストリサーチ(275点満点)
A判定 261(94.9%) B判定 254(92.4%) C判定 246(89.5%) D判定 237(86.2%)
※ボーダー得点 250(90.9%)
昨年度まで250点満点だったので得点率も記載します
1年前 A判定 235(94%) B判定 228(91.2%) C判定 221(88.4%)
D判定 213(85.2%) ※ボーダー得点 225(90%)
2年前 A判定 233(93.2%)B判定 226(90.4%)C判定 219(87.6%)
D判定 210(84%)※ボーダー得点 223(89.2%)
大阪大学 医学部 医学科
2025年度共通テストリサーチ(500点満点)
A判定 470 B判定 457 C判定 443 D判定 430
※ボーダー得点 450
1年前 A判定 465 B判定 452 C判定 438 D判定 425
※ボーダー得点 438
2年前 A判定 460 B判定 447 C判定 432 D判定 415
※ボーダー得点 440
奈良県立医科大学 医学部 医学科(後期)
2025年度共通テストリサーチ(900点満点)
A判定 846 B判定 828 C判定 810 D判定 792
※ボーダー得点 819
1年前 A判定 828 B判定 810 C判定 792 D判定 774
※ボーダー得点 801
2年前 A判定 819 B判定 801 C判定 783 D判定 765
※ボーダー得点 792
昨年から判定基準とボーダーは『1%程度のアップ』
理系最難関といわれる医学部医学科においても、全体的に昨対1%程度のアップとなっています。
■旧帝大 医学部 など最難関医学部
まず共通テストでミスをしていないと思われます。90%を切ってしまった場合は要注意です。
逆に共通テストで上手くいった程度で旧帝大に変えるのは危険です。
合格するであろう層は誰も脱落していませんから、まず自分の二次力を冷静に判断してください。
■神戸・大阪公立・千葉・横浜市立大 医学部 など 都市圏の医学部
共通テストでミスをしたと感じるなら、大人しく志望を下げましょう。
この層も誰も脱落していないと思われますので、ちょっと共通テストで上手くいったからと
喧嘩を売ってはいけません。二次試験に対する準備の差がまともに出るので注意です。
■地方大学 医学部
いつもより共通テストが上手くいった人は、そのアドバンテージを活かしましょう。
この層を目指す人で共通テストを失敗した場合は、医学部に縁がなかった方です。
なぜなら今回の共通テストのレベルで失敗するようでは二次試験で逆転することはそもそも
難しいと理解するべきだからです。自分の点数で確実に戦える大学への出願をオススメします。
ということで、医学部志望者は僅差のところに多くの受験生が集まっていることが十分に考えられます。上位大学になればなるほど、判定は気にせずに自身の二次力と大学別模試の結果を踏まえて出願を検討するべきです。
理系の一般学部においても、おおむね 1%程度のアップとなっています。
理系は二次試験の比率が大きい大学や、科目間で差のある大学もたくさんあります。
それでも、今回の共通テストで C判定 だった人は 逆転は難しいと思った方がいいです。
英語・数学 がそこまで難しいわけでもないのに『C判定しか取れていない』とみるのが賢明で、
ワンランクダウン(共通テストの比重が大きく、B判定以上の判定がでる大学)もしくは、トレンドではない学科(機械系、水産系など)の選択を検討しましょう。
※女子に人気のあった看護、生活科学もトレンドから外れてきているのも最近の傾向※
C判定の場合はどう出願を考えるのか
【国公立大学 文系志望者の場合】
文系の科目は逆転しにくい科目ばかりなので、今までの模試や過去問の出来具合で合格最低点に届くと自信を持てるかどうかが出願の分かれ目になります。
共通テストは周りも取れていることが前提となるので、Cラインでの出願は難しいのが一般論です。
例えば、大阪大学 経済学部 経済・経営 のC配点を考えると・・・
昨年の合格最低点は 398.68/600 だったので、400点を目標とします。
昨年の共通テスト Cライン が237点だったので、上記の目標点数の 400点 から引いた
163点/300点 を二次試験では少なくとも得点する必要があります(概ね55%目標ですね)
今年の共通テストが文系は4%程度ボーダーが上がっていることを考慮して、昨年のCラインを算出し二次試験の目標点数を設定しましょう。
もちろん二次試験も難易度の上下があるので、昨年の問題を解いてみた感触を大事にしましょう!
この得点を取れるイメージが出来ないなら志望大学を下げる判断をする。
希望的観測ではなく、一ヶ月でなんとかなるイメージが持てるかどうかが大事です。
【国公立大学 理系志願者の場合】
理系の場合は、1%程度のアップなので今年の共通テスト得点をそのまま活用できます。
例えば、大阪大学 工学部 応用理工学科 を考えてみましょう。
昨年の合格最低点は 575.11/1000 なので 580点を目標とします。
今年の Cラインは 260/325 ですが、昨年の共通テスト配点が300点なので概算します。
昨年の Cライン概算 240/300 となり、二次目標は 340/700(概ね5割)
この得点率を昨年の問題を解いて取れるイメージを持てるか。
これがCラインで出願するかどうかの判断になります。
理系の受験生は、二次試験の点数が大きくなる大学が多いので『二次で逆転』と考えがちです。
ですが、今年の問題レベルで『C判定しか取れなかった』ことは事実として受け止めるべきです。
加えて、この共通テストで自己ベストかつC判定であれば迷わずに志望校は下げましょう!

まとめ
わずか一ヶ月で夢のような学力の上昇はありません。
まだまだ伸びると思いますが、合格に必要な二次試験の点数を計算した時に、『どうやってこの点数を取るのか』が明確にならない場合は志望変更を検討すべきです。
例えば、数学であと10点、物理であと10点伸ばせば合格できる!というのは妄想です。
数学で頻出かつ失点率が高いベクトルを完答できるように訓練して10点上げる。
あと、学習の不十分な電磁気、とくに電磁誘導の問題を集中的に演習することと、熱力学が疎かになっているのでその演習。完答は出来なくても合計で8~10点は上げれる。
こういった志望大学の出題傾向と自分の現状を比較し、残りの時間を使って実現可能かどうかを
考えることが大事です。
もちろん、それ以外の科目もキープもしくは微増が必要でしょうから、ターゲット科目ばかりに時間をかけていいわけでもありません。
最後は自分で決めるのです。
行きたい!チャレンジしたい!も大事ですが、その前に十分に勝ち筋があるか検討しましょう。
気合根性で合格できるほど、今の大学入試は甘くないのです。
この記事を読んでくれた人は、このまま出願するべきかを悩んでいる人だと思います。
悩む前に自己分析。具体的に頭を動かすことが大事。悩んでも何も解決しません。
戦えるかどうか、どう戦うかを検討して出願するかどうかの答えを出してください。
将来を決める選択だからこそ、悔いの残らないように。
検討を祈っています。